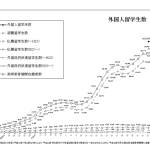新型コロナウイルスの流行により、インターネットを利用した様々な新しいサービスが浸透しました。
「ウェビナー」はその一つで、オンラインでセミナーやイベントを開催することができます。
ウェビナーの特徴は、オフラインでのイベントよりコストや手間を削減でき、大規模なイベントもスムーズに開催できる点にあります。
今回は、そんなウェビナーのメリット・デメリットやおすすめウェビナーツールについてご紹介していきます。
この記事の目次
ウェビナーとは
ウェビナーとは、「ウェブ」と「セミナー」を合わせた造語。その名の通り、インターネットを通じてセミナーを行うことを意味します。
他に、「インターネットセミナー」「オンラインセミナー」「webセミナー」などと呼ばれることもあります。
オフラインでイベントを開くより、場所代や人件費、参加者の交通費といったコストがかからず、また人数制限もなく、誰もが特等席で見られることが特徴となっています。
ただし、事前登録が必要なことや、接続状況によっては配信が安定しないという注意点もあります。
ウェビナーは、詳しく分けるとリアルタイム配信型と録画型の2種類があります。
リアルタイム配信型は、随時参加者の質問を受け付けたり、反応を見ながらセミナーを進められたりするのがメリット。
録画型は接続状況に左右されることがなく安定した配信ができ、視聴者側も好きな時間に視聴できるのが強みです。
開催するセミナーの特性に合わせ、最適な配信方法を選びましょう。
ウェビナーのメリット
それでは、ウェビナーのメリットを詳しく見ていきましょう。
開催コスト・手間を削減できる
ウェビナーのメリット1つ目は、開催コストや手間を削減できることです。
オフラインでセミナーを開催するとなると、事前に開催場所を押さえ、参加者を募集してチケットを郵送し、当日会場で誘導や整理を行うスタッフの配置を決め…と大変な準備が必要です。
しかし、ウェビナーであれば、配信機材を用意して実施日程を決め、開催枠を取って告知するだけです。
また、コストについても、ウェビナーならオフラインイベントにかかる会場費・人件費・交通費などが全て少なく済み、コンパクトに開催することができます。
場所や人数に制限がない
ウェビナーなら、実際に会場を押さえる必要がないので、場所や参加人数に制限がありません。
使用するツールや購入するアドオンにもよりますが、最大1万人ほどの参加者が同時に受講することもできます。
仮に、オフラインで1万人規模のイベントを開こうとすると会場は限られますし、会場使用費や許可取り、当日の誘導配備など膨大な手間とコストがかかります。
ウェビナーは、現実では実現不可能な大規模イベントも、スムーズに開催できるツールです。
受講者の利便性が向上する
ウェビナーは、受講者にとっても様々なメリットがあります。
まず、開催場所までわざわざ出向かなくて良くなるため、移動時間や交通費が節約できること。
オフラインイベントには来ることができない、遠方や海外からの受講者も参加できます。
また、先にも触れましたが大人数での開催も可能なので、行きたいイベントに抽選で落ちてしまうということもありません。
さらに、録画配信なら視聴する時間にも縛られないので、受講者の都合が良いときに観ることができます。
理解しやすいセミナーにできる
ウェビナーは動画でセミナーができるので、文字情報だけでは伝わりにくい複雑な内容も、視覚・聴覚でしっかり理解することができます。
リアルタイム配信型であれば、質問の受け付けや、受講者の反応を見ることができるので、わかりづらかった部分をフォローすることも可能。
録画配信であれば、もう一度聞きたい部分を繰り返し視聴することもできます。
ウェビナーのデメリット・注意点
ウェビナーには、メリットが多いですがデメリットもあります。
ウェビナーを開催する際には、トラブル対策についてもしっかり考えておきましょう。
通信トラブルのリスク
ウェビナーがスムーズに配信できるかどうかは、通信状況に左右されます。
負荷がかかりすぎると、映像が固まったり、音声と映像にズレが出たりして、うまく配信できないのです。
また、マイクやカメラの品質によっては、音割れ・画質の悪さが気になることも。
大規模なウェビナーを開催する前には、機材が適切かどうかや、スムーズに配信できるかどうかを一度予行練習しておくのがおすすめです。
慣れやITスキルが必要
ウェビナーで講義をするときは、実際に対面して話す時とは違った工夫が必要です。
話す早さや声の大きさ、滑舌などの伝わり方が実際とは違うので、配信で好感を与えられる話し方に慣れましょう。
また、ウェビナーで配信するには、機材の接続や動画の録画・編集などに最低限のITスキルが必要になります。
ウェビナーツールはUIの工夫で直感的に使えるものも多いですが、機械に疎い方にとっては開催自体が難しいかもしれません。
参加者の反応が伝わりにくい
講義の内容に参加者がついてきているかどうかや、セミナーを楽しんでいるかどうかがわかりにくいということは、ウェビナーのデメリットと言えます。
ウェビナーでは、開催者側が参加者の反応を見ること自体は可能です。
しかし、現実のセミナーなら目の前の人の表情を見れば一目瞭然ですが、ウェビナーではチャットの文字や、小さなビデオ画面で反応を確認しなければいけません。
ウェビナー成功のポイント
ウェビナーを成功させるには、事前の準備や告知、終わった後の振り返りが大切です。
準備と練習をしておく
先にもお伝えしましたが、ウェビナーと対面では伝わる情報量に差があります。
ビデオだと、よく聞き取れなかったり表情が伝わりにくかったりといったことがあるので、いつもよりゆっくり、はっきりした話し方を心がけましょう。
顔色が悪く見えていないか、女性の場合はメイクが濃すぎない・薄すぎないかどうかも、事前に画面写りを見てチェックしておきます。
カメラやマイクといった機材についても、問題なく接続でき、音質・画質は良いかどうか、照明は適切かどうかを確かめておきましょう。
また、パネリストの顔と同じ背景ばかりが続く講義では、参加者が飽きて集中できなくなる可能性があります。
カメラを複数台用意して適宜画角を変えたり、資料や手元を写すカメラを用意したりするなど、画面に変化を出せるとなお良いでしょう。
開催を宣伝する
ウェビナーは、参加者が集まらなければ開催しても100%の効果を得られません。
自社サイトや、Twitter・Facebook・InstagramといったSNSを駆使して、しっかり宣伝して集客しましょう。
また、ウェビナーには日本国外からも参加できるので、外国語でも宣伝をしたり、海外からのPVが多いメディアに広告を出したりするのも一つの方法です。
データの収集・分析を行う
ウェビナーを継続して開催するなら、開催後のフォローアップも大切です。
参加者にアンケートを行うなどして、どんな部分が評価されたか、どんな課題があるのかを分析しましょう。
開催データをもとにしてブラッシュアップすることで、次回はより効果の高いウェビナーが実現できます。
ウェビナー開催におすすめのツール
最後に、ウェビナー開催におすすめのツールを3つご紹介します。
Zoom Webinar
特徴:最大10,000人と同時接続可能
料金:
基本 無料
プロ 2,000円/月
ビジネス 2,700円/月
エンタープライズ 2,700円/月
Zoom Webinarは、ビデオチャットツールとして有名な「Zoom」の、ウェビナーバージョンです。
Zoomとの違いは、最大10,000人と同時接続が可能なことや、参加者側が視聴のみでも参加できること。
YoutubeやFacebookと連携して、ライブ配信をすることもできます。
有料版なら、ウェビナー終了後にレポート作成機能も使うことができ、登録者、出席者、アンケートへの返答率、出席者のエンゲージメントなどをまとめて把握することができます。
V-CUBEセミナー
特徴:パネリストと受講者の双方向コミュニケーションが充実
料金:要問い合わせ
V-CUBEセミナーは、ウェビナーやオンデマンドコンテンツの配信ができるクラウド型配信サービスです。
受講者との双方向コミュニケーションがしやすいのが特徴で、アンケート機能やチャットなどで効果的に参加者の声を集めることができます。
リアルタイム配信と録画配信がどちらも可能で、さらにタイムシフト(追っかけ再生)も可能。
自由度の高さと、受講者とのコミュニケーションを大切にしたい方におすすめです。
コクリポ
特徴:回線が安定していて繋がりやすい
料金:
基本 無料
ビジネス 30,000円/月
エンタープライズ 70,000円/月
コクリポは、最大300人の同時接続が可能なウェビナーツール。
回線が安定していて、映像が途切れたり固まったりすることが少ないのが魅力です。
万が一接続が切れた場合でも、自動再接続機能があるためストレスなく使用できます。
また、データ集積機能も充実していて、チャットでの発言やアンケートへの回答、滞在時間帯を参加者ごとに把握できるので、細やかなアフターフォローが可能です。
まとめ
ウェビナーは、インターネットを利用することで可能になった新たなイベント開催方法。
感染症のリスクに対策できるのはもちろん、コスト面・労力面で開催側にも参加者側にもメリットがあります。
ただし、接続環境や伝わる情報量の違いなど、ウェビナーならではのデメリット面もあるため、開催するときにはしっかりと対策を考え、十分な準備を行いましょう。