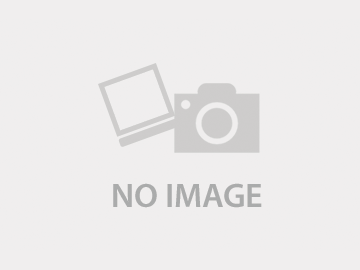ストレスチェックとは、従業員がストレスに関する質問票に回答・分析し、自分のストレス状態を把握するものです。
業務上のストレスが原因の疾患や過労死を防止するために、2015年から一定以上の規模の事業者で実施が義務化されました。
今回は、ストレスチェック義務化の経緯や対象者、実施方法について詳しく解説していきます。
この記事の目次
ストレスチェックが義務化!制度の概要
「労働安全衛生法の一部を改正する法律」により、2015年12月からストレスチェックが義務化されました。
まずは、ストレスチェックが義務化された背景や、対象となる事業所・従業員について知っていきましょう。
義務化の背景・目的
ストレスチェックは従業員が自分のストレス状態を把握し、うつ病など深刻な状態に陥る前に相談・治療といった対策を行うために実施されます。
ストレスチェックが義務化された背景には、劣悪な労働環境と、それが原因となった過労死や自殺があります。
1984年2月、鉄道関連施設の設計等を行なっていた当時31歳の男性の自殺が、日本で初めて「過労自殺」として労災の認定を受けました。この男性は業務から強い精神的・身体的ストレスを受けており、それが原因でうつ病を発症、自殺に繋がったという経緯があります。
これが契機となり、1994年に「労働安全衛生法」が改正され、事業者が努めるべき措置として「労働者のメンタルヘルスケアに取り組むこと」が加えられました。
その後、1998年に「精神障害等の労災認定に係る専門検討会」が発足。
この検討会の調査に基づき、1999年に「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針について」が公示され、精神障害等にかかわる労災認定の判断要件が明確化されました。
その後も過労死や自殺を予防するための取り組みが進められ、2015年に事業者による従業員のストレスチェックが義務付けられたのです。
対象は「労働者が50人以上いる事業所」
ストレスチェックが義務化されているのは、「労働者が50人以上いる事業所」です。
この条件に当てはまる事業所は全て、年1回、対象となる全ての従業員のストレスチェックを実施しなければなりません。
ちなみに、「事業所」とは「働く場所」のことで、ストレスチェックが義務化されているのは会社単位ではなく、「本社」「支店」「工場」など単体で労働者50人を超える場所です。
労働者50人以下の事業所ではストレスチェックは義務ではありませんが、「努力義務」はあり、ストレスチェックをすること自体は可能ですし、した方が望ましいとされています。
ストレスチェックの対象者
ストレスチェックの対象者となる条件は、以下の2つです。
・期間の定めのない労働契約により使用される者(契約期間が1年以上の者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること
・週労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること
つまり、働く予定の期間が1年以上かつ、所定労働時間数の4分の3以上働いていればストレスチェックの対象者です。
契約社員・パート・アルバイトも、上記の条件を満たしている場合は対象者となります。
もちろん国籍も関係なく、外国人であっても対象者となります。
逆に、正社員であっても休職・時短労働などで上記の条件を満たさない場合にはストレスチェック義務化の対象外です。
ちなみに、ストレスチェックの対象となるのは「労働者」のみなので、「使用者」である役員は義務化されていません。
ストレスチェックは誰が行う?
ストレスチェックの実施者となれるのは、以下のいずれかの人です。
・医師
・保健師
・厚生労働大臣が定める研修を修了した看護師もしくは精神保健福祉士
会社・事業所単位でストレスチェックを行う時には、これらの実施者に会社からストレスチェックを依頼します。
一般的には、日頃から労働者と関わることがあり、職場環境をよく知る産業医が実施するのが望ましいとされています。
個人情報保護の観点や、検査結果が人事に影響することを防ぐ目的から、社長・役員・人事部長など労働者に対して人事権を持つ人はストレスチェックの実施者にはなれません。
ストレスチェック制度の流れ
次に、ストレスチェック制度を実施する時の流れを解説します。
ストレスチェックは、
1.事前準備
2.実施
3.説明・報告
4.改善
という4ステップで進めていきます。
事前準備
ストレスチェックを行うための事前準備として、以下のことを決定します。
・制度全体の担当者
・実施事務従事者
・実施対象・日程
・質問票の選定
・実施者・面接指導者の選定
・集団分析の方法
・高ストレス者の選定方法・対応方法
・結果の保存担当者・保存方法
ストレスチェックを実施することが決まったら、従業員に事前に周知します。
ストレスチェックの受診や結果の通知は、本人の同意がないと行うことができません。
何を目的とし、どこで、いつ、どんな検査を行うのかを知らせ、同意を得ましょう。
また、後で詳しく解説しますが、ストレスチェックで得た個人情報は保護され、第三者の目に触れたり人事に影響したりすることはない旨も通知しておきます。
外国人従業員がいる場合には、しっかり理解が得られるよう翻訳版の周知文書・ストレスチェックの質問書も用意しておきましょう。
ストレスチェックの実施
周知が完了したら、質問票を配布してストレスチェックを実施します。
質問票は規定の質問内容が含まれていれば特に指定はありませんが、国が指定する57項目の質問票を用いるのが一般的です。
記入が終わった質問票は、医師などの実施者が回収します。
第三者や人事権を持つ職員は閲覧してはいけないので注意してください。
面談・分析~改善
最後に、実施者が質問票への回答を元に、ストレスの程度を評価します。
高ストレスで医師の面接指導が必要な人がいたら、その人を選出して面談などを行い個別にフォローします。
ストレスチェックの結果や、高ストレス者がいるかどうかは、企業には通知されません。
ストレスチェック義務での罰則
ストレスチェックが義務付けられているにも関わらず、実施していない企業には罰則があります。
労働安全衛生法により、ストレスチェック実施後の報告を怠った事業所には最大50万円の罰金が課せられます。
ストレスチェック自体は実施していても、報告を怠った場合には罰金の対象となるため注意してください。
また、ストレスチェック未実施だと、従業員の安全に十分配慮しなかったとして労働契約法第5条の違反となる可能性も。
安全配慮義務違反を行なっても罪に問われることはありませんが、万が一労働者が業務上のストレスにより疾患を負ったり死亡したりした場合、訴訟で不利になります。
ストレスチェック実施時の注意点
最後に、ストレスチェック実施時の注意点をお伝えします。
個人情報・プライバシー保護
ストレスチェックの内容は、個人のプライバシーに触れる非常にデリケートなものです。
そのため、当事者と実施者以外の第三者に、質問への回答やチェック結果が知られることはあってはなりません。
法律により、ストレスチェックに関わる個人情報を扱う人には守秘義務が課されます。もし違反すれば刑罰の対象となります。
不利益取扱いの防止
ストレスチェックに関して、事業者が以下のことを理由に、労働者に不利な取り扱いを行うのは禁止されています。
これを、「不利益取扱いの防止」といいます。
・医師による面接指導を受けたい旨の申出を行ったこと
・ストレスチェックを受けないこと
・ストレスチェック結果の事業者への提供に同意しないこと
・医師による面接指導の申出を行わないこと
また、ストレスチェックや面接指導の結果を理由として、解雇・雇い止め・退職勧奨・不当な動機、目的による配置転換・職位の変更を行うこともしてはなりません。
まとめ
2015年12月から、労働者が50人以上の事業所でストレスチェックが義務化されています。
50人以下の事業所は、義務ではありませんが努力義務があります。
従業員が安心して働くために、ストレスチェックは必要なものです。
実施しない事業所には罰則もありますので、ストレスチェックは年1回、適切に実施しましょう。