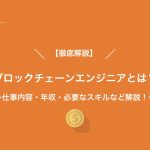これまで新卒採用は、4月に一斉入社する一括採用が一般的でした。
しかし、多様な人材を受け入れるにあたって、「通年採用」という採用方法が注目されてきています。
今回は、通年採用の概要や、メリット・デメリットを詳しく解説いたします。
通年採用を成功させるためのポイントについても、ご紹介していきます。
この記事の目次
通年採用とは?
通年採用とは、文字通り1年を通じて、時期を区切らず採用活動を行うことです。
とは言っても1年間ずっと募集をし続けるという意味ではなく、その時々の必要に合わせて柔軟に募集を行います。
中途採用に関しては、どの企業も通年採用をしているのが当たり前なので、特に区別して「通年採用」という言葉を使うことはありません。
今回は、新卒や第二新卒、帰国子女などを対象とする通年採用について解説します。
海外や外資系企業ではスタンダード

日本企業では、一括で4月入社の新卒採用を行う企業が多数でした。
従来の手法と区別するために「通年採用」という言葉が生まれたのですが、海外ではむしろ通年採用の企業の方がスタンダードです。
そのため、外国人にとっては馴染み深く、外国人採用に向いている採用方法です。
新卒一括採用との違い
通年採用と一括採用の違いは、当然ながら採用を行なっている時期。
新卒一括採用では、解禁日から5ヵ月程度の間(3月~7月ごろ)にまとめて選考を行いますが、通年採用では年間を通して応募に対応しています。
入社の時期もバラバラで、一括採用の場合は入社日まで何ヶ月も開くこともザラですが、通年採用の場合は内定から1ヶ月程度で入社することになります。
通年採用拡大の背景
通年採用が拡大している背景には、留学生や帰国子女が利用する秋採用の増加や、第二新卒の需要の高まりがあります。
日本とは違って、海外の学校は9月が年度始めということが多く、海外の学校を出た新卒者は、日本の学生とは社会人になるタイミングがずれます。
また、若い労働力の不足から、第二新卒や既卒を積極的に採用したい企業も多く、その場合には通年採用の方が効率的なのです。
これまでは、経団連も就職活動が長引くと学生の勉学を妨げるとして、一括採用を推奨していました。
しかし、上記の需要を受けて、通年採用に切り替えていく方針で2018年ごろから制度の変革を始めています。
通年採用のメリット
通年採用には、企業と学生どちらにもメリットがあります。
ここでは企業側のメリットを中心に、通年採用の良いところを解説していきます。
バラエティ豊かな人材と接触できる
通年採用のメリット1つ目は、バラエティ豊かな人材と接触できること。
通年採用なら、企業ごとの募集時期がバラバラなので学生も様々な企業を検討でき、企業と会社が接触する機会が多くなるのです。
従来の一括採用では、同時期に複数の選考を受けるため、学生側も企業に優先順位をつけなければいけません。
結果人気の有名企業にばかり学生が集まり、中小企業やBtoB企業は学生と接触する数自体が少なくなってしまいます。
グローバルな採用ができる
新卒一括採用では、海外の学校を卒業して帰国・来日した外国人や留学生、海外の大学出身者には、出会う機会がありません。
なぜなら、先にも少し触れましたが、海外の学校の多くは9月が年度始めだから。
また、学校にもよりますが、アメリカの一部の大学などは必要な単位が取れたら卒業となるため、人によって卒業する時期がバラバラなこともあります。
通年採用は、レベルの高い外国人人材や、帰国子女を採用するチャンスです。
自由・慎重に選考できる
通年採用には、一括採用のように決まったスケジュールがありません。
そのため、時間にこだわらず応募者としっかり対話をして、慎重に選考することができます。
面接を重ねて相互理解を深めることで、入社後のミスマッチを防ぐことにも繋がります。
逆に、急いで人材を確保したい場合には、スピーディーに採用を決めることも可能です。
数合わせの内定・採用が不要
通年採用では、もし辞退者が出ても通年募集を行なっているので、人数を補完しやすいです。
内定辞退を防ぐために、入社までフォローを行うという手間もなくなります。
一括採用の場合だと、何人かには内定辞退されることを見越して、多めに内定を出しておくということがあります。
予想より多く辞退者が出てしまった場合、期限までに予定採用者数に合わせるのが難しいこともあります。
学生側のメリット
学生側のメリットとしては、短期間に多数の企業を回る必要がなく、ゆとりを持って就活ができることが挙げられます。
内定を貰えないままほとんどの企業の募集期間が終わってしまい、就活に失敗するというリスクも少なくなるでしょう。
さらに、海外留学など多様な経験・活動を生かして就活ができるため、学生時代にできることが広がるというメリットもあります。
通年採用のデメリット

通年採用には、メリットだけではなくデメリットもあります。
デメリット面も検討して、自社で導入するかどうか決める必要があるでしょう。
採用コストや採用担当者の負担が増える
通年採用の場合は、採用期間が長いため人事担当者の負担が大きくなります。
人事担当者が総務などの仕事も兼任している場合は、スケジュール管理に注意が必要です。
一括採用だと、募集開始から内定を出すまでのスケジュールが決まっています。
人事担当者は採用期間以外では、他の業務に専念するということも可能です。
また、求人広告も通年出しておく必要があったり、イベント出席の機会が増えたりなど、トータルコストも高くなりがちです。
入社時期がバラバラなので、研修や教育も分けて行う必要があり、そこでもコストがかかるでしょう。
知名度が低い中小企業には不利
一括採用の場合、学生は解禁日周辺に一斉に求人情報をチェックするので、知名度の低い企業の求人もそこで目に留まる可能性があります。
大手企業が採用を早めに締め切るので、そこで落ちた学生が中小企業に回ってくるということも。
しかし、通年採用の場合、「入れそうな企業の募集を探す」のではなく「入りたい企業の募集を待つ」というイメージです。
そのため、そもそもの知名度が低いと学生の目に留まらず、応募が集まらないと言う可能性があります。
応募者の数・質が落ちる可能性も
日本では、まだ通年採用が主流というわけではありません。
他の企業が一括採用を行なっている時期に募集をしていないと、そちらに学生を取られてしまいかねません。
また、通年採用を行なっていると、他の企業と被っていない時期に「暇だからとりあえず受けておこう」という志望度の低い応募者が混ざってしまうこともあります。
通年採用を行なっていることで、「いつでも受けられる企業」として滑り止め扱いをされる可能性もあるのです。
学生側のデメリット
学生側のデメリットとしては、希望の企業がいつ募集を行うかわからないため、就活期間が長引く可能性があること。
また、企業が慎重に学生を吟味できるため、採用のハードルは全体的に上がります。
さらに、知名度の低い企業の求人は見つけにくいので、積極的に業界研究をする必要が出てきます。
通年採用を成功させるポイント
最後に、通年採用を成功させるための3つのポイントをご紹介します。
採用エリアを広げる
通年採用を行うと、一度の募集に集まる応募者数が少なくなることが予想できます。
その場合は、自社の近隣エリアだけではなく、広いエリアでの募集を行うと良いでしょう。
例えば、まだ帰国・来日していない留学生や外国人にアピールできるよう、英語や海外ドメインのリクルートサイトを作るなど。
web説明会やオンライン面接を導入すると、遠方の学生ともコンタクトを取ることが可能です。
リクルートサイトの見直し
リクルートサイトは、学生に自社をよく知ってもらうための窓口です。
通年採用に対応して、何度も説明会を開くのはコスト的に難しいという企業では、いつでも誰でも見られるリクルートサイトの内容に凝るのがおすすめです。
採用したい人材のペルソナを明確に定めて、効果的にアプローチできるサイトを作成しましょう。
採用業務を効率化する
通年採用では、人事担当者の負担が大きくなりがちです。
管理システムやツールを導入して、機械に任せられる部分は任せ、業務を効率化すると良いでしょう。
外部の採用サービスを活用するのも、一つの方法です。
また、外国人や遠方の学生向けにWeb面接を取り入れると、学生・人事担当者ともに面接に取られる時間が減り、他の業務に集中できます。
まとめ
通年採用は外国人や帰国者、第二新卒などの採用需要の高まりにより、注目されてきています。
スケジュールにゆとりを持って採用ができるため、企業にも学生にもメリットは多いです。
しかし、導入を始めるにあたっては、業務の効率化やリクルートサイトの内容など、見直しを行うべき部分もあります。
外国人採用に注目している企業では、ぜひ通年採用を検討してみてください。